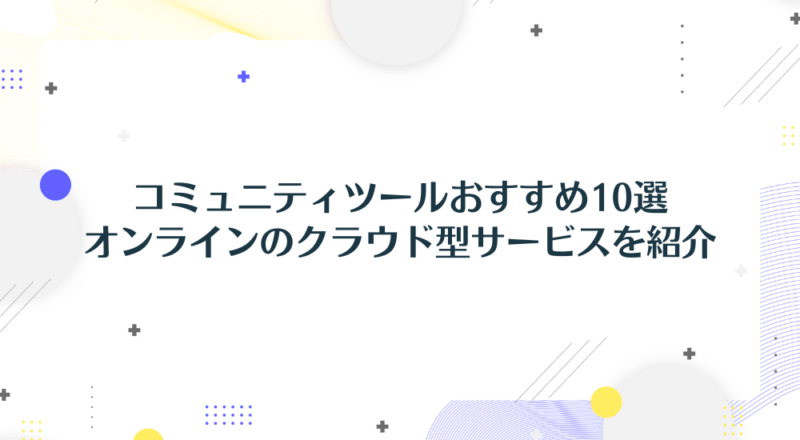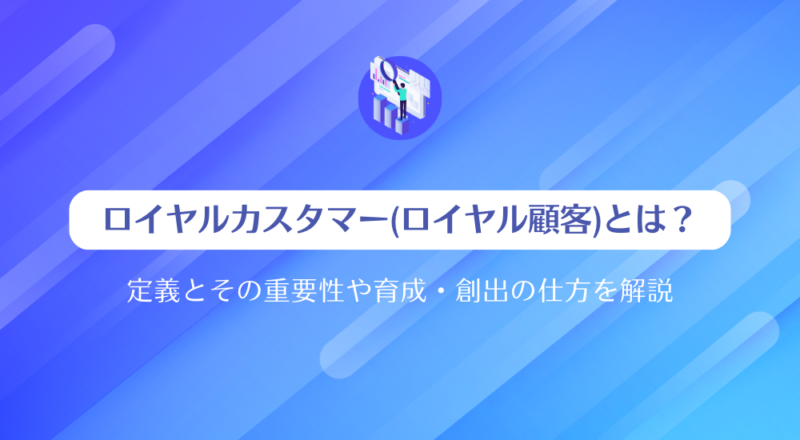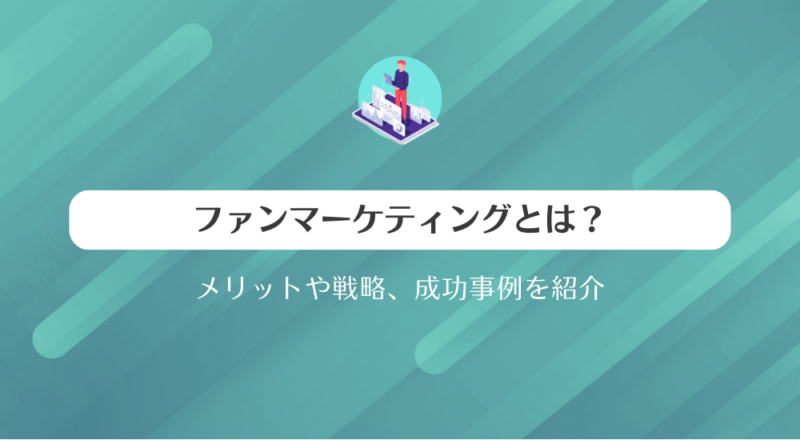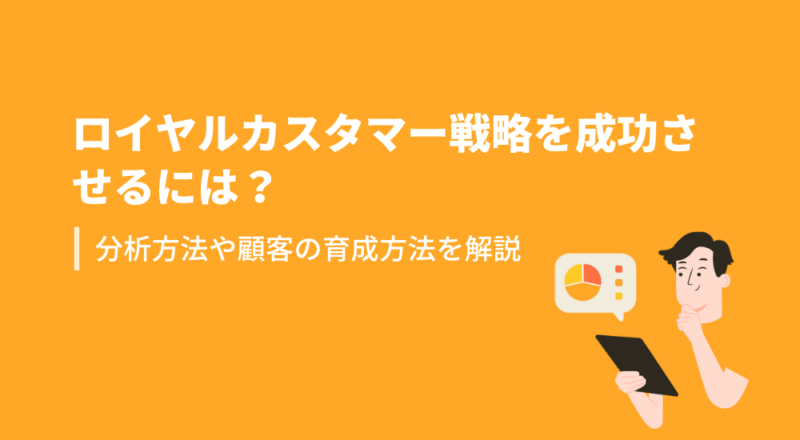2020年5月21日に開催したオンライン対談イベント『【これからのコミュニティ論】オンラインコミュニティを活用し顧客ロイヤリティを向上させる方法』にて、コミュニティの運営に注力されているお二人にご登壇いただきました。
イベントではオンラインコミュニティの活用法について、前半は小父内 信也 氏に「コミュニティ論」を、後半は岩城 佳那 氏にヤッホーブルーイングでの具体例をお話いただいております。
今回イベントに参加頂けなかった方にもお楽しみ頂けるよう、本レポートではイベントの内容をダイジェストでお届けします。
岩城 佳那 氏 (以下、岩城)
株式会社ヤッホーブルーイング「よなよなエールFUN×FAN団」ユニットディレクター
Twitter:@yohobrewing (よなよなエール/ヤッホーブルーイング公式)
小父内 信也 氏 (以下、小父内)
Sansan株式会社 Eightコミュニティマネージャー 兼 株式会社Asobica CCO
Twitter:@obushin
Eight:https://8card.net/p/obuobu
オンラインの利点と欠点
小父内:
今、新型コロナウイルスの影響で状況が大きく変わり、オフラインでのコミュニティ活動が難しい状況が続いています。そこで今回は、このコロナ禍においてコミュニティをどう活用すればよいのか、またオンラインでコミュニティを上手く運営していくための方法やコツを、岩城さんとお話ししていこうと思います。よろしくお願いいたします。

当日資料「【これからのコミュニティ論】オンラインコミュニティを活用し顧客ロイヤリティを向上させる方法」より抜粋
そもそも、「オンラインって何がいいの」となった時に、1つ目は距離の制約を取り払えることが大きいと思います。
名刺アプリEightには日本全国に260万人のユーザーさんがいるのですが、オフラインでは大きな都市でのユーザーイベント開催がメインでした。ただ、先日実施したオンラインイベントでは、福岡と仙台の方が「どうも初めまして!」と挨拶出来たのはオンラインならではの新鮮な体験でした。
あとはイベント自体の運営も、オフラインだとケータリングや飲み物、また大きい会場だと会場代も結構かかったり、それに伴うスタッフの配置だったりと開催コストが高くかかってしまうこともあるので、オンラインイベントで『コストを抑えられる』というのはイベント開催に踏み出しやすくなった点だと思います。
そして今の状況、なかなか直接お会いできないこともあって、皆さん『つながり』を欲していますね。だからこそオンラインでもすごく高い熱量を維持したまま、開催出来る部分があると思います。

お話をする小父内 氏(編集部注:当日はオンラインWebツール(ウェビナー形式)を使用し、参加者の顔は見えない形で対談を行っておりました。)
反対にオフラインの難しいところはまず、”期待値”の調整です。
直接相手の目を見て話せるオフラインとは全然違って、オンラインだと目線や表情、細かな反応などの情報量が圧倒的に少なくなります。それは話し手にとっては特に大変で、今この瞬間も実はチャットの反応以外の情報がないので、一方的に話している感じがするんですよね。
その場合、話し手は参加者に満足して貰えるようにイベントをスムーズに進めていくことが難しくなります。そのため、担当者の「ファシリテーション力」はすごく求められますね。
また、社内でオンラインイベントを提案する際は「どのくらい費用対効果があるか」と聞かれると思いますが、ここも事前にすり合わせをしておかないといけない部分だと思います。
なぜかと言うと、オンラインイベントでは母数の申込数は上がりますが、参加率は下がる傾向があるからです。特に有料のオフラインイベントの場合、参加率はあまり下がらないのに対して、出入り自由が主のオンラインイベントでは歩留まりが3割下がるというのが僕の経験則としてあります。
もう一つ難しい点は、スター候補の見極めです。
コミュニティの立ち上げの大事なステップとして、コミュニティの核となるリーダーのような方の選定があると思いますが、やはり対面に比べて『この人はどんな人なんだろう』という感覚的な見極めが難しくなります。だから、あえて僕はオンラインの1on1対談をやったりしています。
※最近では、2on2を推奨するケースが増えております。
今までだとイベントの時に話しかけて、「僕はこういう想いを持っているんです」など話をしていくことでその見極めが出来ていましたが、オンラインではそれが出来ないので、チャットで「オンラインでお話しませんか」と送ったりしています。
ただし、このやり方は、コミュニティを大きくしたり、自走させたりする方法には至っていないので、まだまだ違うやり方を模索していかなければと思っています。
成長するコミュニティの3要素
成長するコミュニティの必須要素は、大きくまとめると3つあります。
1つ目が『情熱』の部分です。よなよなエールさんであれば「よなよなエールが好きだ!」や、「ヤッホーブルーイングが好きだ!」といった情熱です。プロダクトやサービスへの想いがあってこそ、人は惹きつけられるのです。
2つ目は、『コミュニティデザイン』の部分。「これからコミュニティをどう構築するのか」というロードマップをしっかり持っているかどうかです。建物でいう基礎の部分ですね。
最後に、『テクニック』の部分ですね。単純にZoomやRemo(オンラインカンファレンスツール)の効果的な使い方を知っているかとか、誰にどのタイミングでどういった声掛けをするかといったテクニカルな部分はすごく重要ですね。

当日資料「【これからのコミュニティ論】オンラインコミュニティを活用し顧客ロイヤリティを向上させる方法」より抜粋
今まではこのテクニカルな部分、いわゆる『戦略性』よりも、一緒に盛り上がるという『情緒性』に訴えかけることによって、問題なく成り立っていました。ただ、これからはオンラインが主流になってきます。そうなると、情緒と合わせて戦略をきちんと組み立てていかないと、コミュニティはなかなか火がつかないと思います。
成功するオンラインイベントの5か条
そして、オンラインイベントを成功させるカギは5つあります。
1つ目は事前の準備です。リハーサル、アナウンス文章や告知URLの用意、メッセージを出すタイミングを全部事前に仕込むこと。イベントの成功はこの事前準備で9割決まると思っています。
2つ目は、一方向になりやすいコミュニケーションをいかにケアするかです。質問のタイミングをしっかりと設けたり、イベントの目的を全員が共有できる仕掛けをしたりといったことが大切です。
3つ目は、イベント運営をサポートする裏方の存在です。
このイベントにも3人の裏方がいて、タイムキープなどをしています。これを1人でやるのは本当に難しいです。画面に向かって話しているので、どうしても、なかなか質問を拾いきれなかったり、時間を気にしなくなってしまったりということが発生します。だから、誰かアシスタントが一人、二人いるだけでもイベントの質は違うものになります。
そして4つ目が「常に現在地を意識する」ということです。
話し手だけでなく、聞き手も「今何について話しているか」が分かるようにすることも大事です。というのも、オンラインだと途中参加が結構多く、「10分ぐらい遅れてきたら何話してるのか全然わからない」ということもあり得ます。パート毎でいいので、自分が何を話すのかを明確にできたらいいと思います。
最後は、お土産です。今までは最後の集合写真などを配布できましたが、オンラインでは出来ません。例えば今日であれば発表資料の共有ですが、何か持ち帰るお土産があると参加者の満足度も上がりやすいかと思います。
よなよなエールコミュニティの文化

「超宴」の楽しい雰囲気が伝わる背景写真でお話をする岩城 氏
岩城:
ヤッホーブルーイングは、地ビールブームの真っ只中に創業し、最初はブームに乗り、業績は好調でした。しかし、ブームが去ると次第に「地ビールは価格が高く、味が個性的すぎて、品質の悪いものがある」と思われるようになり、弊社も打撃を受けました。
その中で、藁にも縋る想いで始めたのが通信販売です。
商品の販売ページを作成したり、メールマガジンを配信したりといったことを継続することで、次第にインターネットを通じたお客様との直接の接点が増えていきました。店頭で売れなくなってしまっても、支持してくれるお客様は通販で買い続けてくれて、応援の声をかけてくれました。
当時通販サイトの運営をしていた現在の社長・井手はお客様の応援の声に感動し、「やはりファンを大切にしなくてはいけない」と思ったそうです。これが、ファンを大事にする原体験であり、現在のファンを大切にする活動につながっています。
弊社には「価値観」として掲げるいくつか文言の一つに「顧客は友人、社員は家族 」という言葉があって、社員同士、顧客間でもニックネームで呼び合うようなフラットな文化があります。イベントではスタッフとファンの見分けがつかないほどです。
よなよな流、ファンを巻き込むコミュニティの在り方

「当日資料「よなよな流・ファンを巻き込んだオンラインコミュニティのあり方」より抜粋(ヤッホーブルーイング・岩城 氏)
弊社のファンが集うコミュニティとして、「よなよなエールコミュニティ」というライトなファン向けのオンラインコミュニティがあります。立ち上げ当初、参加者はは100名程だったのですが、今は1000名近くメンバーがいて、ライトなファンやコアなファン、社員、公式ビアレストランの従業員からお客様まで、さまざまな立場の方が参加しています。
コンスタントにポストを投稿するのは数十名のコアなファンたちですが、良いバランスだと思っています。コアなファンたちが、イベントや弊社のビールを飲んで得たポジティブな体験を、どんどん投稿してくださります。そこに他のファンがコメントを付けて交流をしている。
そんな様子を、すごくライトなファンにも見てもらい「よなよなの世界っていいな~」と感じてもらえる。それも、スタッフの積極的な手入れ無しにです。これは、自走するコミュニティとしてはすごくいい例じゃないかなと思います。
イベントでは、イベント動員数と業績が強い相関系を持ち続けています。

「当日資料「よなよな流・ファンを巻き込んだオンラインコミュニティのあり方」より抜粋(ヤッホーブルーイング・岩城 氏)
弊社では、事後アンケートの熱狂度とNPSを掛け合わせて見ています。実際、どちらも高いお客様は明確にLTVが高いです。そして、ロイヤリティが高いお客様は弊社を守るような行動もしてくれます。
例えば、以前イベントチケットの販売広告をフェイスブックに出稿した際、批判コメントがついたんですよね。もちろんスタッフもレスポンスしていましたが、とあるコアなファンの方が、その批判コメントに対してとってもポジティブなコミュニケーションをとって、フォローしてくださいました。
また、「ファン宴」と銘打って、ファンの方たちが自主的にイベントを企画・開催してくださったり、コミュニティを盛り上げてくださいます。

「当日資料「よなよな流・ファンを巻き込んだオンラインコミュニティのあり方」より抜粋(ヤッホーブルーイング・岩城 氏)
コミュニティの「ミソ」
コミュニティのミソは、ファンとメーカーの双方向の関係だけではなく、ファンとファン同士が横のつながりを作ることだと思います。オンラインではこれが難しく、私達がやっているYouTube配信も、コメントを拾いながら頑張っていますが、ファン同士のつながりをつくるという点では課題も感じています。
この配信も今までリスナー100人程でやっていましたが、コロナの状況下で繋がりへの需要が高まり、今では500人規模になりました。
5/30(土),6/6(土)には大型オンラインイベント「よなよなエールの“おうち”超宴」を初めて開催します。私達が勇気をもってこのようなチャレンジできる強みとして、今までやってきたオフラインのコミュニティ活動の『コミュニケーション貯金』がある、既に火がついているファンがいるということがあります。
コミュニティ立ち上げのコツ
小父内:
先ほど『コミュケーションの貯金』と仰っていましたが、本当にこれは大事だと思います。よく「オンラインコミュニティはどうやるんですか」と相談が来るんですが、「じゃあ今までは何をしていましたか」という話で。やはり最初からいきなりオンラインで成功するというのは難しいです。
ただ、今の状況的に「そうは言っても」という場合もあるので、そういうときは、私は1on1を提案しています。
コミュニティはこちらが一方的にデザインして与えるものではないので、一緒に運営していくリーダーが必要になってきます。そして、そのためにはお互いの信頼が必要となるので、その信頼作りから始めるべきだと考えるからです。
もう一つのアドバイスは、最初は少人数から始めるという事です。最初はコア層を集めて骨組みを作って、それから輪を広げていく。焚き火理論の話だと、最初からキャンプファイヤーにするのではなくて、焚き火から始めるということですね。
岩城:
確かに。焚き火をすっ飛ばすと、結果何にもならないことがありますね。小さくても、まずは確実に燃える火を付けることが大事ですね。
小父内:
ピンチをチャンスに変えて、みんなでオンラインコミュニティやっていきましょう!
CXinでは、カスタマーサクセス担当者・コミュニティ運営担当社・これから取り組みたい企業様に向けて、参考になる情報を少しでも広く届けたいという思いから、オンラインイベントを行っております。
(現在、月1回ペースで開催中)
次回イベント情報
※画像をクリックすると、申込フォームが開きます。
▼日時
2020年6月25日(木) 15:00〜16:00
▼テーマ
「【CS最前線】オンラインでのつながりを切り開いた3社が語る、コミュニティの今」〜mercari × note × Eight SPECIAL TALK〜
ご興味のある方は、是非お申し込み下さい。
なお、最新のイベント情報はCXinの公式Twitter(@CXin2020)でも発信しておりますので、こちらのフォローもよろしくお願い致します。