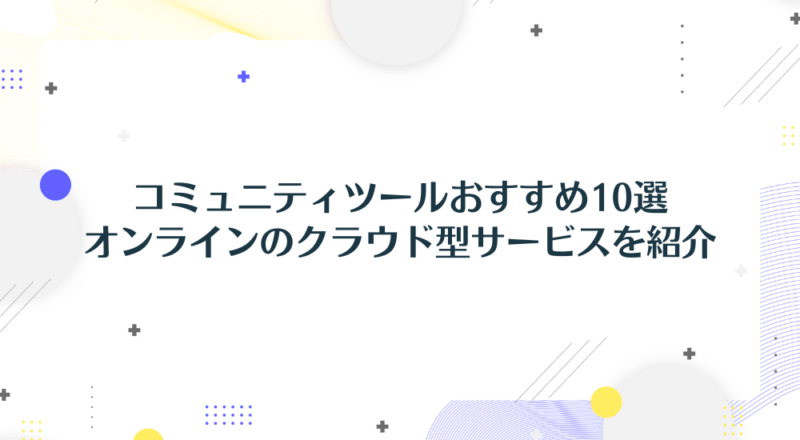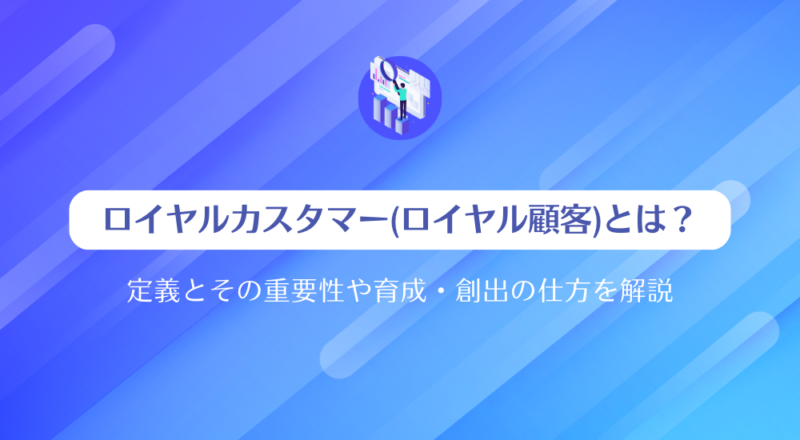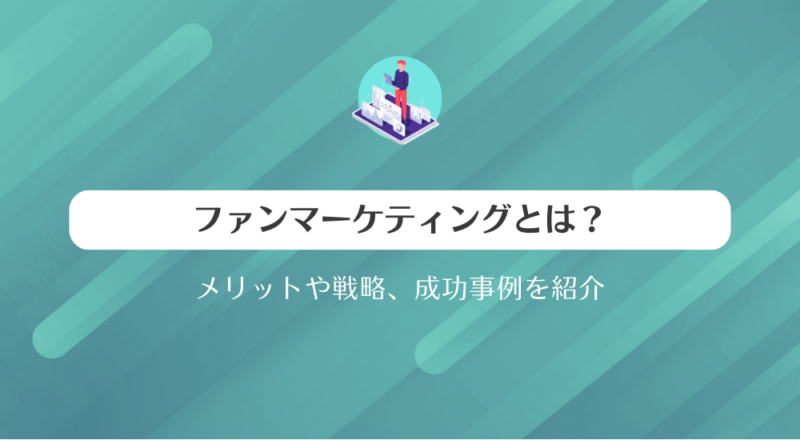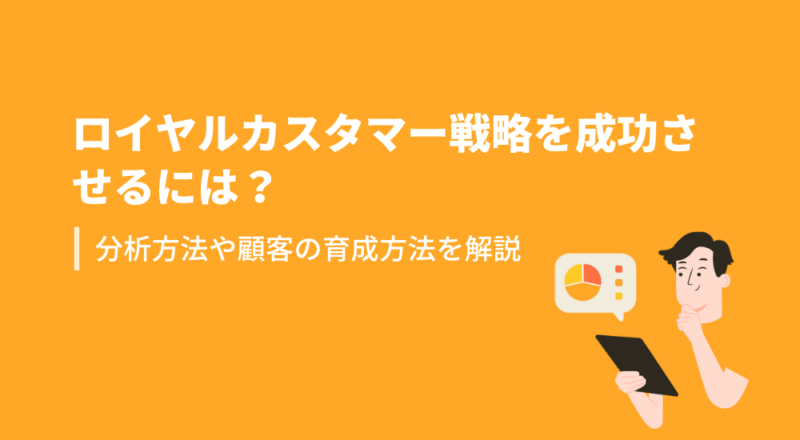「出会いからイノベーションを生み出す」をミッションに掲げるSansan株式会社にて、ユーザー数250万人以上の名刺アプリEightのコミュニティマネージャーを務め、2019年10月にコミュニティ関連のコンサルティングを行う合同会社Obuを立ち上げ&株式会社AsobicaCCOに就任した小父内 信也さんに、Eight事業部でのコミュニティチーム立ち上げの裏側と今後のコミュニティの未来についてお聞きしました。
小父内 信也氏
株式会社Asobica 取締役CCO
Sansan株式会社 Eightコミュニティマネージャー2010年、名刺管理システムのSansan株式会社に入社。データ化部門責任者を経て、名刺アプリEightのコミュニティマネージャーへ。2019年に株式会社Asobicaに取締役CCOとして参画。
−小父内さんのこれまでのキャリアと現在のお仕事について教えて下さい。
僕は、20歳の時に大学を辞めたんですね。その頃、音楽で食べていきたいという夢があったので、昼間は工事現場で働いて、夜はラッパーとしてクラブ巡りをしてという生活を5年ほどしていました。でも、中々音楽では食べて行けず、夢を諦めて地元の小田原に帰ったんです。そこで、幼稚園の時の同級生とすぐに結婚することになって。「あっやばい、就職しなきゃ」となりまして(笑)
中学校の同級生の紹介で一部上場企業の電子メーカーの工場で働き始めました。ただ、それはあまり刺激がないというか、物足りなかったんですね。自分よりも一回りも二回りも年上の方ばかりで、なかなか僕の意見は聞きいれてもらえませんでした。でも、頑張らなくてはという気持ちはあったので、毎日朝4時半に起きて猛勉強して、中小企業診断士という資格を取りました。本も年間300冊くらい読んでいました。
その頃に、今度は高校の同級生が名刺管理システムのSansan株式会社に入ったんです。その同級生に誘われて、当時、市ヶ谷にあったSansanに遊びに行きました。そうしたら、その日のうちに代表と取締役から「入社して欲しい」と言われたんです。でも、その時僕は断りました。絶対に行かないと(笑)
そこから半年間、代表の寺田や誘ってくれた同級生からの猛アタックが続きました。最後は寺田が小田原の僕の家まで来たりして、そんな風に時間を過ごしていくと改めてすごい熱意で誘ってくれていると感動したんですね。そしてこの人たちは本気で世界を変えようとしている集団なんだと強く感じたんです。そんな経緯もあってSansanへ入社を決めました。
Sansanでは、データ化部門の立ち上げからセンター運営など全体の統括を6年半やってから、新しいチャレンジとして名刺アプリEightの部門に移りました。Eightは基本的に無料のサービスなので、当時は多くのリソースをサポートに割くことが難しい状況でした。だからこそ、ユーザーさんを知ることの必要性に気付いて、サポートチームを立ち上げることにしました。そうした中で段々と役割が増えていって、サポート/カスタマーサクセスの派生から最終的にコミュニティに行き着いて、コミュニティマネージャーをやっていました。そして今は、コミュニティ関連のコンサルティングの行う合同会社を立ち上げて代表をしています。
ユーザーは神様ではなく、仲間

−Eightでのコミュニティ立ち上げまでは、どういう形で進んだのでしょうか?
サポートチームでは、日々改善要望やご質問などを頂きますが、お問い合わせすること自体、ユーザーさんにとって労力が掛かることだと思います。でも、それをわざわざしてくれるのは、Eightへの愛があるからだということに気付きました。そんな気付きから、ユーザーさんに直接会ってみたいなと思うようになったんです。それから、ユーザーさんと会うことを何回か繰り返して、僕と広報の担当者と超熱いユーザーさん2人の4人でグループを作ったことが始まりでした。
−最初からユーザーさんを中に巻き込んだんですね。
そうです。最初から巻き込んで、僕の気持ちを正直に話しました。「Eightは、ユーザーの皆さんを大切に思っている」「もっとユーザーさんと向き合っていきたい」と。それで前述の4人グループから始めて、2018年8月にユーザーさん20人を招いて初めてのユーザー会を開催しました。結果は、成功も失敗もありましたね(笑) その会ではユーザーさんは”神様”だと思って、すごくおもてなしをして、喜んではもらったのですが、その分、時間やコスト、エネルギーをかけすぎて、再現性がないイベントになってしまったんです。
ただ、そこからの学びで私自身の考え方は大きく変わりました。ユーザーさんは神様ではなく、“仲間”だと。未来を切り開く、出会いを変えていくツールがEightであって、実体験はユーザーさん自身が持っている。つまり、ユーザーさんも未来を変えていく仲間だということに気付いたのです。それに気付いてから、共感してくれるコミュニティメンバーがどんどん膨らんでいきました。
−メンバーはどうやって増やしていったのですか?
定量と定性を掛け合わせた上位ユーザーを抽出して、全国主要都市で開催するユーザー会に招待していました。Sansanはデータドリブンの会社なので、データからヘビーユーザーとか、スーパースターを見つけることが得意なのです。だから、定量面はそういったデータの分析を徹底して行っていました。定性面では、Eightでの投稿内容やその他SNSも観られる範囲でどういう人なのかを確認したりしていました。そうして抽出されたユーザーさんに参加してもらう会を1年間で十数回実施して、どんどん輪を広げていった形です。そこからオンラインに融合させました。
コミュニティが上手く秘訣は「ちょい出しのリーク」

−コミュニティ立ち上げを始められた時、会社としてはコミュニティの優先順位はそれほど高くなかったとお聞きしましたが、いかがだったのでしょうか。
やっぱりコミュニティって時間がかかるものなのですよね。それはよく言われることですし、本当にそういうものだって今も実感していますが、1~3ヶ月で芽なんか出ないです。だから、短期目線で結果を求められてしまうと結構難しいですね。ただ、当然事業を成り立たせなくてはいけないから、結果はどうだという話になりがちです。そこをきちんと理解してもらって、ユーザーさんと向き合うには長い目で見ないといけないよねという理解を得ることが非常に重要でした。リソースも十分にあるわけではなかったので 、理解を得られるまでは自分の往復4時間の通勤時間(前述の通り、小父内さんは小田原在住)を使ってユーザーさんとのやり取りをしていました。だから、そこは僕の地の利じゃないですけど、有利だったところかもしれないですね。入社してからずっと人より1.5倍ぐらい働いていた感覚はありましたね。でも、段々そうやっていると仲間でもあるユーザーさんが助けてくれるようになりましたね。どんどんフォローもしてくれますし、盛り上げてくれたし、彼らがいるから支えられました。
−コミュニティに対して、会社側の理解を得るには、どうするべきでしょうか?
やって見せるしか出来ないですね。そこをそれぞれのステークホルダーにどう適切に当てるかはテクニカルな部分もありますし、コミュニティマネージャーが責任を持つところだと思います。極論ですが、僕は、絶対に結果は後からついてくるのでコミュニティにKPIは要らないと思っています。ただ、最初にやるには説明責任としてKPIが必要なので、仮説としての定量目標を置くようにしていました。事業を加速させる数字なり結果は、後から絶対ついてきます。
何故そんな風に言えるかというと、Eightでそれを経験したからです。僕は、ユーザーさんから半年間で100件近くのフィードバックを貰いました。100件のフィードバックって、お金に変えられないじゃないですか。今はアンケートを出すと1日で50本ぐらい返って来ることもあります。更にすごいのが、コミュニティに属するユーザーの皆さんがすごい数の新規ユーザーを呼んでくれていることです。もう、それが全てですよね。信頼できる人がクチコミで周囲の人に声をかけてくれると。だって、SNSなどで広告を出したりすると、かなりの金額をかけてたりするじゃないですか。無償でEightが好きだから、便利だから使いなよと宣伝してくれるなんて、本当に嬉しいことです。ユーザーフィードバックを得られるし、ヒアリングも出来るし、リファラルしてくれるし、プロダクトの改善案を出してくれるし、コミュニティがあったからこそ、嬉しいことがたくさんありました。
−コミュニティが上手くワークするための秘訣があれば教えて下さい。
仕掛けは色々とあります。例えば、「ちょい出しのリーク」ですね。明日リリースのものを前日に少し早いタイミングでお伝えするとか。後は、ユーザーさんの声に素早く反応することはすごく重視していました。オンラインで改善要望等が上がってきますが、そこに上がったものにすぐに対応することは、僕の責務としてやっていましたね。例えば不具合だったら、見つけた瞬間に開発に流して修正して貰って、3時間後には直っているとか。ユーザーさんの声を聞くためにABテストをやって、結果をすぐに反映させるとか。そうするとユーザーさんも頼られて嬉しいですし、場も盛り上がるので、仕掛けとしても反応の速さは意識していました。
−ということは、ユーザーさんの声をいかに入ってくるかというところが大事なんですね。
そうですね。僕の役割はハートの部分だと思っていたので、それに対してものすごい責任感を持ってやっていました。ただ、全ては応えられないので100言われたうちの10でも返すぐらいですけれども。でも、伝えることは100%やっていました。僕の中で、コミュニティは信頼なのです。だから、誰でも入れる訳ではなく、きちんと慎重に選定していました。だからみんなも安心出来るし、そこは成功要因の一つだと思います。
コミュマネの資質は、サービスが好きで、余白が作れる人

−どういう人がコミュニティマネージャーに向いていますか?
大きく言うと2つあると思っています。1つは、そのサービス/プロダクトが大好きな人です。そうじゃないと言っていることが嘘になるので、そんなコミュニティマネージャーはやっぱり透けてバレてしまいます。今年の4月、僕はEightユーザー250万人の中で投稿数や反響でトップクラスのヘビーユーザーになりました。なので自らがEightのユーザーとしても自信を持っています。
もう1つが、広い視野を持っている人ですね。空間把握能力とでも表現できるのでしょうか。俯瞰して物事を見られるかどうか、空気を読めるかどうかは非常に重要です。ユーザー会の場である人の飲み物が足りないから注いであげるとか、一人ぽつんとしている人がいるなとか、そういう目配り、気配りが出来る人は向いています。それが出来ないと、知らず知らずのうちに「場」としてのコミュニティが冷めてきたり、妙な雰囲気になってしまったりするのです。オフラインで出来ないことはオンラインでも当然出来ないので、それはどちらにも共通していますね。
もう少し言うと、この2つ以外にも「余白」を作れることが必要だなと思っています。コミュニティは色々な凸凹があって、みんなでそこの役割を埋めていく共生の場所なんですよ。だから、そこを完璧に仕上げてしまうようなことは不要なんです。コミュニティとしての信頼の場が築けていれば、時には盛り下がってもいいですし、一部の人が盛り上がっても良いんです。トータルで見たときに、コミュニティ全体がより良い雰囲気、チームになっていることが大切ですね。
−小父内さんが考える、今後のコミュニティの可能性はどういったところにありますか?
僕は、コミュニティはブランドの顔だと思っていて、プロダクトがユーザーにいかに向き合っているかを示すものだと思っています。ユーザー抜きには何も語れないので、向き合うことが必要なんです。だから、僕はコミュニティを世の中に広げていきたい。この先の世界では、一つのコミュニティに属するだけじゃなく、いくつものコミュニティを行き来する中でその人というアイデンティティが育まれていって、それが掛け合わさった時により大きな化学反応が起きていくと思っています。
だから、この先やりたいのは、Eightのコミュニティだったり、いくつかある他のコミュニティだったりを掛け合わせて、シナジーを生んでいきたいんです。単なるマルチコミュニティから、クロスコミュニティへの進化です。昔の地域コミュニティみたいなものだと、そこに合わないと行き場がなくなってしまうので、無理矢理にでもそこに合わせるしかなくなってしまいますよね。でも、今はオン/オフ構わず色々なところに顔を出せるので、そういう意味では、生活の一部だし、そこに対して出入りも自由だし、やはり居心地の良さでコミュニティを求めていくみたいなことは、この先どんどん広がっていくでしょうね。
そもそもコミュニティという言葉がなくなっていくのではと感じることもあります。今は、便利な言葉としてものすごく広義の意味でコミュニティという言葉が使われています。でも、プロダクトのコミュニティもあれば、地域のコミュニティ、特定の業界を巻き込むコミュニティなど千差万別です。基本は、共通の関心事について、集う集団です。将来的には、あちこちでいくつものそういった集団に属して、自分というアイデンティティを確立していく時代がくるとそう思っています。そして自分としては、世界を楽しくワクワクできるような1つのコミュニティにしていきたいです。